【MFA健康コラムVol.37】ストレスへの理解 その1
3月の健康コラムで「ストレスへの向き合い方」を紹介した。今回は、そもそも「ストレス」とは何か?を掘り下げたいと思う。
さて、皆さんは最近ストレスを感じた事があるだろうか?また、そのストレスは皆さんにどのような影響を及ぼしているだろうか?
ストレスと聞くと「ネガティブ」なことと捉えがちになる人も少なくないだろう。
でももしその「ストレス」が人間にとって必要なものだとしたら、どうだろうか。
昨年から続く大きな時代のうねりの中において、多くの「ストレス」を抱え、感じている人も多いだろう。その解決の糸口になるかは個人の状況下によるだろうが、解釈の一つとして参考にして頂ければ幸いである。
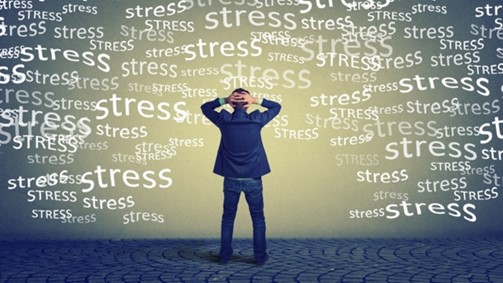
【ストレスとは?】
「スタンフォードのストレスを力に変える教科書」にて著者のケリー・マクゴナガルは、ストレスとは「自分にとって大切なものが脅かされる時に生じるものである」と述べている。
自分の思い入れのある物事に感情が左右されたことが、皆さんもあるのではないだろうか。そのうちの一つが喜びであったり悲しみであったり、そして「ストレス」であったことがあるだろう。
例えば「3秒でこの絵の中から間違いを探してください!」と言われれば、3秒しかないからと焦ってしまい集中力が下がり実力を発揮できない時もあったり、そうなる人もいるだろう。逆にその瞬間に集中力が上がる時もあったり、そうなる人もいるだろう。
両者とも、同じ「3秒で!」というストレスをかけられているのだが、状況によって、個々によって反応の仕方に差が生まれるのである。
人間の脳はストレスによってパフォーマンスを下げることがある一方、パフォーマンスが高まる場合もある。つまり、ストレスには悪い点もあれば良い点もあるということだ。
そしてストレス反応そのものは、私たちが生命活動をしていく上で必要だからこそ備わっている重要な仕組みなのだ。
先の「3秒で!」の、状況や人によってパフォーマンスに差が出ることからもわかるように、自分と他人のストレス反応のありようを同一視しない方が良い。自分がある刺激に対してストレス反応をしてしまうからといって、他の人にも当てはまるとは限らないからだ。
つまり、自分はある刺激を受けてもストレスを感じないからといって、他人に同じことを押し付けてはいけない。逆に、自分にとって大きなストレスでも、他人にとって大したストレスではないこともある。

人によってストレス反応のあり方が異なってくるため、ストレスとうまく付き合う上でも人間関係を高める上でも、まずは自他のストレス反応のあり方を同一視しないことが重要となる。
中には「ストレスなど直視したくない!」と考える人もいるだろう。
しかし、人間は生きているだけで外部環境からストレスを受けている。それにより適正な幅でリズムを刻み健康を保っている。ストレスがあるからこそ人間の恒常性は活かされている、というのも一つの解釈となってくる。
ストレスに目を向けることで、ストレスを味方にして成長することも可能となるのだ。

皆さんはどのようなものにストレスを感じるだろうか?
また、その時の思考の変化、体の変化にはどんなものがあるだろうか?
今一度、考えてみて欲しい。
参考書籍
「スタンフォードのストレスを力に変える教科書」ケリー・マクゴナガル
「ブレインドリブン」青砥瑞人
【MFA健康コラムVol.31】ストレスの向き合い方 その1
【MFA健康コラムVol.32】ストレスの向き合い方 その2
【MFA健康コラムVol.33】吐き出すことで起こる変化 その1
【MFA健康コラムVol.34】吐き出すことで起こる変化 その2



